| HOME | RQE | RQC | RDE | RQEのご購入 |
| RQE HOME PAGE >RQE >品質工学のページ | |||||
|
品質工学とは 品質工学とは、田口玄一先生が提唱する技術開発・製品設計・工程設計・工程管理における品質とコストの改善を行う技術的対策の体系で、開発設計や工程設計の技術開発に関する機能性の評価と改善をおもに扱うオフラインの品質工学、生産工程の調整問題を扱うオンライン品質工学に大別することができます。
この中で、品質工学の中心的課題は、市場で起きるトラブルをいかに予測し、技術開発研究段階で品質を能率的に改善するかにあると思います。品質を合理的に改善するには、能率の悪い品質特性を調べるのではなく、いかに消費者要求以前の機能の安定性を改善するかが重要です。品質特性はあくまでも結果でしかないかです。
具体的には、あらゆる機能はエネルギーの変換であるという考えのもとに、そのシステムの入力と出力の関係を理想に近づけるための機能性の研究を行います。ほとんどの機能の理想関係は、入力信号をM、出力特性をyとするとy=βMとなるので、その理想関係からのばらつきの比較研究を行うことになります。実験では、広範囲の製品に使える技術を開発するために、できるだけ広い範囲の信号を選択し、また、入力関係を理想機能から乱す変数(ノイズ)を取り上げ、このデータから機能性の測度である、動的SN比と感度Sを求めます。SN比と感度Sを改善するためには、さまざまな設計定数をとりあげることが重要です。
しかしこのような考え方はいままでほとんど用いられることがなく、故障や騒音など顧客の要求品質で評価を行ってきた場合がほとんどでした。品質工学では、製品企画前に、このような機能の安定性の研究を行い、基本機能に対する基礎技術を蓄積しておき、製品設計や生産工程の設計段階では、主に目標値にあわせるチューニング作業だけで製品設計や工程設計を完了させることをすすめています。
技術開発における機能性の研究は、製品企画前に行うことができ、さまざまな品種や将来の製品に役立つ有用な技術であり、価格や品質の面で競争力のある製品を能率良く開発・生産する上で、今後ますます各企業で取り入れられていくことでしょう。
詳しくは、はじめての品質工学セミナールームをご参照ください。
実験を行う際の基本的な考え方 私たちが実験を行う際にまず考えなければならないことは、製品の目的特性や目的機能ではなく、 そのシステムがどのような技術的手段により目標を達成しているかという事である。 品質工学では、目標を達成するための技術的な手段を「システムの基本機能」と呼んでいる。
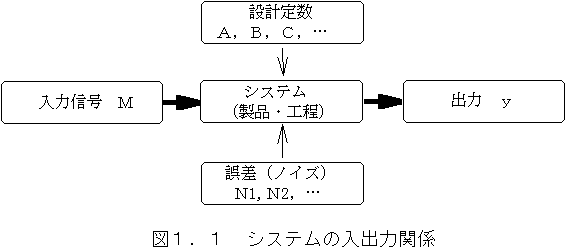
あらゆるシステムは入力としての信号と出力の関係を利用して目的を達成している。(図1.1)
市場で製品がおこすほとんどの品質問題が、システムの基本機能の乱れによるものである。例えばデジタル複写機の場合、信号であるパルスの数により画像のパターンを形成するが、 市場で起きるいろいろなノイズにより、出力である画像は影響を受ける。 ここでは計測上の制約から画像濃度を計測特性にしたとする。
仮に信号がゼロから255の範囲をとるとき、理想的な関係は信号がゼロの時画像は形成されず、 信号に比例して濃度が濃くなり(ドットパターンが密になる)、信号が255のときベタとなることである。
この比例関係からの乱れが市場における品質問題となる。
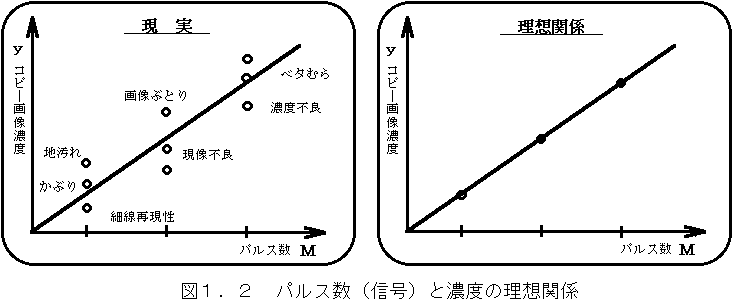
たとえば図1.2に示すように、信号がゼロなのに画像が形成されるのが地汚れであり、信号の出力通り画像が形成されないのが濃度不良やベタムラである。画像品質を特性値として解析することは、検査が目的であれば問題はないが、設計開発という面では非常に効率の悪い方法である。たとえば、地汚れによる解析を行い最適条件を求めても、濃度も出なくなったというのでは問題があるからである。
私たちは、個々の品質特性を取り上げるのではなく、入力と出力の関係を理想関係に近づけることにより、副作用に変換されるエネルギーを減少させ、画像品質を改善することを考える必要がある。
複写機の画像の場合もそうであるが、入力信号をM、出力をyとしたとき、システムの理想関係は、多くの場合次の比例式となる。
y=βM … (1)
しかし、実際のシステムは、設計者が制御できない誤差因子の影響(X1,X2,…,Xn) を受け次の複雑な関係で与えられる。
y=f(M, X1,X2,…,Xn) … (2)
たとえば、コピー画像の濃度の場合は、環境の影響、使用する紙の種類や状態、感光体の劣化等により、複雑な関係となる。しかし、その関係を正しく求めることは、技術開発の効率化ではほとんど無意味である。
重要なことは、様々な使用条件で(誤差因子の影響)で、特性値がどう変化するかを知ることではなく、特性値ができるだけばらつかないようなシステムのパラメータの水準値をさがすことである。誤差の影響は認めた上で、設計者が制御できる制御因子の水準値を変えることにより、いかに(2)式を(1)式に近づけられるかを検討することが、パラメータ設計であり、機能性の研究である。
機能性の研究は、特定の製品や仕様に対する品質改善とは違い、製品企画より前に先行して行うことができ、広い範囲の製品に有用な技術である。以下に、品質工学の基本的な実験の手順を示すので参考としてほしい。
品質工学の基本的な実験の手順
- まず、私たちは最初にシステムの基本機能を定義し、その理想関係を考えることから始めることになる。基本機能の機能性を評価するための特性値は、計測方法を考慮し、決める必要がある。計測できない場合は、代用特性を考える必要があるからである。
- 大きなシステムや制御系を含む場合は、モジュールに分解し理想機能の定義を行う。
- 理想機能の定義が終わったら、信号因子の範囲と誤差因子の範囲を予測する。信号因子はゼロ付近も含めてできるだけ広く、誤差因子は意図的に調合してデータをばらつかせ、必要最小限のデータを計測する。データから、有用部分である比例項の変動β2と有害部分である比例項からの距離の2乗和σ2を求め次のSN比を定義する。(η=β2/σ2)
- SN比や要因効果の計算及び、最適条件の推定を行う。データ処理は、コンピュータを利用し、効率よく行うことにより、解析時間を短縮し、計算ミスを防止できる。
- 現状と最適条件の利得が再現するかどうか確認実験を行う。
品質工学会について 品質工学の共通の研究の場として1993年品質工学会が設立されました。品質工学会は、品質工学に関する情報を一元化し、品質工学の普及、発展を目的としています。また、年6回の機関紙の発行、年1回の研究発表大会が実施されています。
みなさんも是非、品質工学会に参加なさってみていかがでしょうか。
- 品質工学会連絡先:〒107 東京都港区赤坂4−1−24
日本規格協会内 品質工学事務局
TEL:03-3583-8008
FAX:03-3582-0698
品質工学研究発表大会品質工学賞について
財団法人精密測定技術振興財団より品質工学研究発表大会にて発表された事例を対象として、その独創性や成果が優秀であると思われる事例に毎年品質工学賞が贈呈されています。 RQE作者は第一回品質工学研究発表大会にて、精密測定技術振興財団品質工学賞銀賞をいただきました。 表彰状とトロフィーはこちらに展示しています。 研究発表大会品質工学賞受賞者については、ここをクリックしてください。
第一回・・・パラメータ設計のための特性値
FAQ (よくあるご質問とその回答集です)
例題による解析例 (RQEの解析手順はこちらを見てください)