
 |
直交表とその役割 |
前回、外側のわりつけと誤差因子の調合についてお話をしました。
今回は、内側のわりつけに、なぜ直交表をお勧めしているのかについてお話をしたいと思います。
 |
直交表の役割 |
|
何度も言うように、パラメータ設計の場合、通常、内側に制御因子を、外側に誤差因子・信号因子をわりつけます。
そして、まず外側因子にわりつけられた信号因子と誤差因子からSN比を求めます。 SN比を求めるということは、信号因子の効果を維持しながら、誤差の影響ができるだけ少ない制御因子の組み合わせを探すということです。 すなわち、誤差との交互作用を利用し、異なる条件への再現性のある制御因子の組み合わせを探しているのですが、制御因子どうしのSN比に対する交互作用がないことの保証はできません。 そこで、異なる条件への再現性への検査をするために、直交表を用いることになります。 具体的には、直交表に主効果のみをわりつけ、交互作用を交絡させた実験をおこないます。そして主効果のみで最適条件の推定を行い利得を計算します。 そして確認実験で、「その利得が再現するかどうか」を調べて、最適条件で取り上げた制御因子の主効果が信用できるかどうかを検証する必要があります。 SN比を求めることは、誤差に影響されない制御因子の組み合わせを選ぶことなので、もちろん制御因子どうしの交互作用も小さくする方向を選ぶことにつながると思いますが、最適条件を決める際に、直交表を用いて、主効果をくつがえすような交互作用がないかどうかを確認することが異なる条件での再現性のために必要だと思います。 直交表を用いることによって、「最適条件の選択」の誤りをチェックすることができ、間違った実験結果を後工程に流すことを防止することができます。 品質工学では、異なる下流条件での再現性の検査として利用する点が、従来の実験計画法と大きく異なる点の一つだと思います。 | |
 主効果と交互作用
主効果と交互作用
|
|
|
パラメータ設計では、直交表に交互作用(制御因子の組み合わせによる効果)をわりつけたり、最適条件を求める時に交互作用を利用することはお勧めできません。 なぜならば交互作用が大きいということは制御因子の最適水準が、他の制御因子の水準により異なることを意味しているので、異なる下流条件でまた、最適条件が変わる可能性が高いからです。 我々企業の目的は、限られた特殊な条件である研究室の中で、すばらしい性能をあげる製品を設計することではなく、研究室の条件とは異なる生産工程や市場条件でも安定して機能する製品を設計することだということを忘れてはいけません。 そのためには、主効果(他の制御因子の水準が変わったときの平均の効果)の積み重ねで最適条件を求める必要があります。 そしてその主効果の大きさくつがえす大きな交互作用がないことを検査する必要があります。そのために使用されるのが、直交表です。
| |
 直交表について
直交表について
|
|
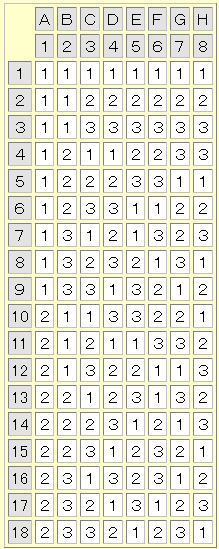 直交表には、L4,L8,L12,L16などの2水準系直交表とL9,L18,L27,L36などの3水準系直交表があります。
直交表には、L4,L8,L12,L16などの2水準系直交表とL9,L18,L27,L36などの3水準系直交表があります。
このなかで、L12,L18,L36は交互作用が特定列に現れない分散型と呼ばれています。 交互作用分散型は、直交表に主効果のみをわりつけ、交互作用を交絡させた実験をおこない、主効果をくつがえすような交互作用がないかどうかを確認するのに大変適しています。パラメータ設計時、L18をお勧めしている理由の一つが交互作用分散型だということです。 直交表の組み合わせは、「1つの列の各水準の中に、他の列の各水準がすべて同回数ずつ現れる」という性質を持っています。このことを直交している」と呼んでいます。
左は、よく使用するL18直交表です。 たとえば、1から8列に、AからHという因子を8個わりつけたとします。 AとBを見てみましょう。 A1の水準(実験№1~№9)にはB1が3回、B2が3回、C3が3回現れています。 また、A2の水準(実験№10~№18)にはB1が3回、B2が3回、C3が3回現れています。 BとCはどうでしょうか。
B1の水準(実験№1~3,10~12)にはC1が2回、C2が2回、C3が2回現れています。 「どの列」と「どの列」を見ても直交している事が分かると思います。 他の列の各水準がすべて同回数ずつ現れている(直交している)ので、A1とA2の優劣を比較しようとしたとき、他の因子の影響はキャンセルすることができ、(実験№1~№9)と(実験№10~№18)の平均値を使用することができます。 いいかえれば、他の因子をある条件で固定して比較するのではなく、他の因子の条件をいろいろ変えた条件下で平均値を計算し比較することができます。 すなわち、他の因子の条件をいろいろ変えた条件下で平均値を求めるということは、他の因子が変わっても一貫した効果をもつもののみが、主効果として推定されることになります。主効果は、他の因子の条件が少し位変わっても水準の優劣が逆転しない因子に重点を置いているため、規模という一つの条件が変わっても実験室の結果が生産の場や市場で再現する確立が高くなるということです。 しかし、それはその主効果の大きさくつがえす大きな交互作用がないことを保証しているのではありません。直交表で求めた主効果から計算した利得を、確認実験で検証する必要があります。 主効果が交互作用より十分に大きく信用できるものであれば、その利得は確認実験で再現することになります。
| |
 |
 |
 第一回・・・パラメータ設計のための特性値 第一回・・・パラメータ設計のための特性値
|
| 品質技術支援サイト ≪HOME≫ | ||||
| RDE | ||||