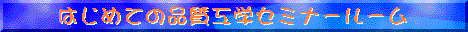実際には、ばらつきの大きさを信号の大きさで割ったもの逆数をSN比と呼ぶ。その対数の10倍がデシベル単位のSN比である。品質工学ではdb単位を使う。
 |
SN比の求め方 |
|
各実験ごとのSN比の求めかたは、まず信号と測定データから理想とする1本の直線を引く。
理想となる直線の直線の傾きは後で調整すればよいので、その直線は、測定データから直線までの出力のばらつきが最小になるゼロを通る直線である。(ゼロ点比例式の場合) そしてそのばらつきσの2乗和を、直線の傾きβ(感度)の2乗で割ったものの逆数をもとに対数をとる。直線からのばらつきだけで判定すると傾きが小さいほどSN比がよくなってしまう。感度との比をとることにより傾きが違うデータも同じように比較できる。制御因子ごとのSN比は、各実験のSN比を足しあわせて平均値をとったもの。 |






品質工学では制御因子をできるだけ取り上げ、直交表の組み合わせに従って実験を行い、それぞれの制御因子ごとに最もSN比の高い条件を選んで、最適条件を求める。最適条件は、それぞれの制御因子が他の因子の影響を受けずに,単独で安定性を高くできるような因子の水準の組み合わせである。最適条件による改善度合いは、計算による推定だけでなく、確認実験と呼ぶ最適条件を用いた実際の試験により検証する。改善度合いが確認実験で再現すれば、各制御因子の組み合わせによる影響(交互作用)が少なく下流への再現が高いことが証明される。実験では、市場や大規模生産など条件が変わっても再現する最適条件を求めることが重要である。直交表を用いることにより、その再現性をチェックすることができる。
※ この用語集は、日経メカニカル(1997.11)にも掲載。