
 |
望目特性とゼロ望目特性 |
よく、「RQEのSN比変換のメニューにゼロ望目の感度がないのはなぜか?」「望目特性とゼロ望目はどう違うのか?」というご質問をいただきます。
また、ゼロ望目特性を使用しなければいけない特性値に、望小特性を適用している事例を見かけることがあります。
今回は、「望目特性とゼロ望目特性」また「ゼロ望目特性と望小特性」の違いについて一度整理しておきたいと思います。
 |
望目特性(ゼロ望目特性を含む)とは |
|
望目特性(ゼロ望目特性を含む)とは、ある有限の目標値があって、目標値よりも小さくても大きくても良くない特性です。
望目特性(ゼロ望目特性を含む)の解析では、ロバストネス(安定性)の改善と出力のチューニング作業という2つのステップをとります。 ロバストネス(安定性)の改善で、利用されるのがSN比、そして、出力のチューニング作業で利用されるのが感度です。
具体的には、要因効果図から各因子ともSN比の一番高いところ選択して、まず安定性の改善を行います。
このときの出力が目標値に一致すればこんないい事はありませんが、実際には一致することはまずありません。
SN比と感度の要因効果図を利用し、SN比に影響が大きく、感度になるべく影響が無い因子を探します。
そしてその因子を利用して、そのときの目標値との差分を調整します。
ある目標値がある場合でも、目標値にこだわらないでSN比を改善したあと、SN比になるべく影響のない因子で出力を調整する(安定性を確保したまま出力を調整する)ことが、この望目特性の解析の大きな特徴です。 望目特性は、計測特性の性質によって大きく2種類に分けることができます。 一つは、寸法とか時間とか負にならない場合で、通常単に「望目特性」と呼ばれるのは、計測特性が負にならない場合です。 もう一つは、計測特性が負の値をとり得る場合で、製品の反りや位置ずれなど、目標値がゼロの場合が多いので「ゼロ望目特性」と呼ばれています。 (以降、計測特性が負にならない場合を「望目特性」、計測特性が負の値をとり得る場合を「ゼロ望目特性」と呼びます。) | |
 「望目特性」−計測特性が負にならない場合−
「望目特性」−計測特性が負にならない場合−
|
|
|
計測特性が負にならない望目特性の場合、SN比は平均値mと標準偏差σの比の2乗になります。 分散だけでは最適条件を求めることはできません。分散が2/3になっても平均値が半分になってしまうのでは誤差率がふえてしまうからです。 平均値がゼロになれば、分散もゼロになることからも判ると思います。 すなわち、計測特性が負にならない(ゼロに壁がある)場合は、ばらつきは出力により左右されるので(出力が大きければばらつきは当然大きくなるので)、変動係数(標準偏差/平均値)の逆数の2乗をSN比として計算します。 感度は平均値の2乗です。計算上では、この値にlogをとります。
SN比=10*log(m**2/ve)
logをとるのは、利得の加法性のためです。 負にならない望目特性の場合、RQEのSN比変換メニューから「望目特性」を選択して、生データファイルから2つの新しいファイル(SN比・感度)を作成する必要があります。
| |
 「ゼロ望目特性」−計測特性が負の値をとり得る場合−
「ゼロ望目特性」−計測特性が負の値をとり得る場合−
|
|
|
負にならない望目特性の場合、SN比は平均値mと標準偏差σの比の2乗でした。 しかし、負の値をとる場合の分散は平均値によって影響されないため、分散の小さくなる条件を選べばよいことになります。 すなわち、データが負の値をとり得る場合は、ばらつきは出力に左右されないと考えることができるので、標準偏差の2乗の逆数をSN比とします。 SN比=10*log(1/σ**2)=-10Log(σ**2) logをとるのは、やはり利得の加法性のためです。 こちらのSN比が、通常ゼロ望目と呼ばれています。 感度は、データ自身にゼロに壁がないので、平均値をそのまま使用することができます。 S=平均値 計測特性が負の値をとり得る場合の望目特性の場合は、RQEのSN比変換メニューから「ゼロ望目特性」を選択して、新しいファイル(SN比)を作成する必要があります。 ゼロ望目の感度を解析する場合は、SN比変換変換は必要ありません。 そのまま平均値の解析を行ってください。 (計測データを、SN比変換をしないで、そのまま解析してください) この場合も計測特性が負にならない望目特性と同様に、はじめは目標値にこだわらないでSN比を改善し、次にSN比に関係がより少ない要因で感度Sを目標値に調節します。 間違えないで欲しいのは「ゼロ望目特性」は、計測特性が負の値をとり得る場合で、目標値はゼロでなくてもかまわないということです。 | |
 |
ゼロ望目特性(望小特性との混同) |
|
計測特性が負の値をとり、ある有限の目標値がある場合、ゼロ望目特性を使用します。 目標値はゼロでなくてもかまいませんが、目標値がゼロの場合が多いので、「ゼロ望目特性」と呼ばれています。 ゼロ望目特性で間違いが多いのは、望小特性との混同です。 たとえば、製品の反りや位置ずれなどを、ゼロからの差分をデータとして、望小特性で解析している事例をよく見かけます。 反りや位置ずれなど方向性のあるデータの場合、プラス側に反りが起こる(位置ずれがおきる)のか、マイナス側に反りが起こるのか(位置ずれがおきる)のかが、とても大切な情報です。 ゼロからの差分をデータとするのではなく、必ず、プラスマイナスのデータを計測し、ゼロ望目特性を使用して解析を行います。 望小特性はあくまでも非負のデータの解析に使用して下さい。 (ゼロからはるかに遠いところの解析では、近似的に望小特性としてもかまいません)
| |
SN比の説明は第三回・・・SN比とその種類を参照して下さい。
望目特性の手順は第八回・・・最適条件を推定してみよう(2)を参照して下さい。
 |
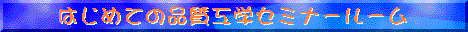 |
 第一回・・・パラメータ設計のための特性値 第一回・・・パラメータ設計のための特性値
|
| 品質技術支援サイト ≪HOME≫ | ||||
| RDE | ||||