
 |
動特性それとも静特性? |
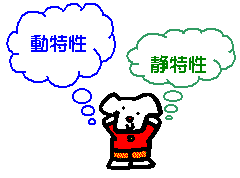 今回は、品質特性を解析したときの問題点と、動特性と静特性の関係について考えてみたいと思います。
今回は、品質特性を解析したときの問題点と、動特性と静特性の関係について考えてみたいと思います。
メーカーが製造している製品には、多くの品質機能がありそれぞれにその仕様があります。
たとえば複写機の場合、作像プロセスだけでも画像濃度、地汚れ、解像力、階調性、濃度ムラ、ベタ均一性など、数多くの品質特性があり、それぞれの項目に対して仕様が細かく決められています。
「黒い紙をコピーした場合、画像の濃度がどのくらいなくてはいけない」
「線はどのくらいの細線までコピーできなくてはいけない」
「画像がない場所には当然汚れがあってはいけない」といったものです。
これらは、市場で起こる品質上のトラブルを防ぐために考えられたもので、検査では重要です。
しかし、品質特性は、最終的な目的でしかないため、改善のための特性値としては不適当です。
品質特性を解析特性とした場合の問題点は、おおきな3つの問題点があります。
1番目の問題は、特性値の加法性の問題です。
たとえば、不良率などの特性値は、データが大きすぎて不良なのか小さすぎて不良なのかわかりません。汚れなども、何が原因で起きているのかそれにより対策も違います。
当然加法性はないわけです。真円度とか、騒音などもその例です。
品質特性を用いて実験を行った場合、当然、実験結果の再現性が悪くなり(交互作用が大きくなる可能性が大きくなり)、実験が失敗に終わる確立も多くなります。
2番目の問題は、多特性の問題です。品質特性による解析は、どうしても多くの特性値を評価することになります。
また、一つの不具合を解決しようとしたら、違う問題が出てくることも数多くあります。
たとえば「騒音が問題なので、防振ゴムやカバーを追加したら、今度は発熱が問題になった。」「コピーの地汚れを特性値に実験を行い、最適条件を求めたら汚れはなくなったけど、今度は濃度不良が起きてしまった。」
等など・・・
3番目の問題は、データの再利用ができないということです。 品質特性のデータは個別の製品ごとのデータでしかないため、一部でも設計変更があったとき再び実験を行いデータを取る必要があります。
このような問題を解決するには、どうしたらよいのででしょうか。
そもそも、騒音や振動などの品質特性は、なぜ起きるのでしょうか。
あらゆる機能は、エネルギーの変換です。エネルギーの変換ロスが、騒音や発熱などの副作用を引き起こします。
最終的な目的を評価する前に、システムの機能のエネルギー変換効率を上げ、副作用の原因となるエネルギー損失をできるだけ少なくすることが大切です。
品質の改善を期待するのであれば、個々の品質特性を取り上げるのではなく、目的を達成するための技術的な手段「システムの基本機能」を評価します。
システムの入力と出力の関係を理想機能に近づけることにより、副作用に変換されるエネルギーを減少させ、品質項目を改善することを最初に考える必要があります。
技術者は、材料開発から大きなシステムの開発まで、かならず、その物性や機能を利用して研究を行っています。
そして入力と出力の関係を利用してシステムの設計を行います。
たとえば、抵抗は電圧を電流に変換するのが機能です。
複写機の用紙送り機構では、ローラーの回転数で用紙の搬送距離を制御します。
射出成形は、金型寸法を製品寸法に転写する技術です。
デジタル印刷機は、原稿パターンを電気信号に変換し、電気信号で発熱体素子の熱エネルギーを制御します。そして、マスター孔を穿孔して、そこにインキを通過させ、画像パターンを形成します。
この関係を、安定性の測度の動的SN比におとして、それを解析することが機能性の研究です。
機能性のロバストネスの研究データは、製品ごとのデータではありません。その機能を利用する多くの製品に利用できるデータです。 それは企業の技術力となります。また、入出力の比例関係を改善することにより、比例関係が乱れたときの結果である品質特性を改善しようという考え方は、基本機能という1つ特性値にまとめることができ、当然、加法性が高く再現性もあります。 これが、動特性の考え方です。動的SN比を用い最適条件を求めることにより上記で指摘した3つの問題は、クリアーすることができます。
上記で説明したように、動特性の理想関係は、いろいろな使用条件や環境下でも、入力信号と出力の関係が乱れず、比例関係になってくれることです。 そして通常は、入力信号がゼロのとき出力がゼロであることが明白なので、特殊な事情がない限り、ゼロ点比例式を利用します。
補足・・・
基準点とそのデータの情報により、動特性は次の3つの種類に分類できます。
ゼロ点比例式 信号がゼロの時、出力がゼロであることが明白な場合 基準点比例式 信号がある値のとき、その出力の値が明白な場合 一次式 基準点とその出力が不明な場合
品質工学では、品質を次の4段階に分類しています。機能のばらつきを改善したいのであれば、源流で研究(動特性を利用した研究)を行うことが重要となってきます。
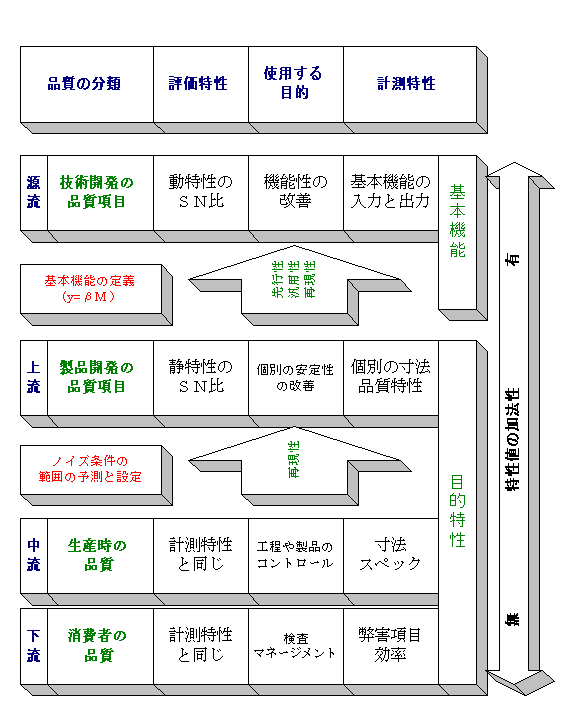
では、基本機能の理想関係が不明の場合や、計測上の制約がある場合、職場での立場や納期的な問題で品質特性しか計測できない場合や、信号を固定した実験しか行うことができない場合はどうしたらよいでしょうか・・・
そのような時のために、静特性が用意されています。
確かに、品質特性での解析は上記で指摘したような数多くの問題をかかえています。
しかしいろいろな使用条件や環境下でデーターを求め、平均値とばらつきの改善を行う静特性を解析特性に使用することにより、スペックのみの評価に比べて再現性という面で大きな改善があります。
もちろん計測特性そのものの加法性が心配ですので、直交表による再現性のチェックを行い、再現するかどうか確認実験を必ず行って下さい。
静特性には大きく分けて4つの種類(望小特性・望大特性・望目特性・ゼロ望目)があり、それぞれ理想状態が何かにより使い分けて下さい。
比例関係からのずれ(品質特性)を特性値として直接解析するのが望小特性です。
比例関係の乱れがなく傾きを大きくしたい場合の代用的な方法として望大特性があります。
信号が1水準しか取れないまたは信号因子が不明の場合の解析方法として望目特性が用意されています。
また、計測特性が負の値を取る場合の望目特性としてゼロ望目特性があります。
静特性の場合、必ず心配されるノイズ(定性的な誤差因子)を取り上げることが動特性より重要です。
特に望目特性の場合は、平均値をばらつきを別々に解析特性とするので、必ず定性的な誤差を取り上げて下さい。
「動特性での解析ができない場合、静特性が必要となってくる」と私たちは考えています。
SN比の説明は第三回・・・SN比とその種類を参照して下さい。
 |
 |
 第一回・・・パラメータ設計のための特性値 第一回・・・パラメータ設計のための特性値
|
| 品質技術支援サイト ≪HOME≫ | ||||
| RDE | ||||