


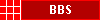
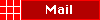
|
—Ю |
|
|
|
|
|
үh—{Һm |
үh—{ӮМғoғүғ“ғXӮМӮЖӮкӮҪҢЈ—§ӮрҚмҗ¬Ӯ·ӮйҗHҺ–ҠЗ—қӮИӮЗүh—{Һw “ұӮр’КӮөӮДҒA Ң’ҚN•ЫҺқҒE‘қҗiҒAҺҫ•aӮМ—\–hҒAҺҫ•aӮрҺқӮВҗlӮЙӮ»ӮМ ҺЎ—ГӮрӮ·Ӯ·ӮЯӮйҒA җк–еҗEӮМҚ‘үЖҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB |
|
|
|
үоҢмҺxүҮҗк–еҲх (ғPғAғ}ғlҒ[ғWғғ Ғ[) |
Ңц“IүоҢм•ЫҢҜҗ§“xӮМӮаӮЖҒAҺs’¬‘әӮМҲП‘хӮрҺуӮҜӮД–K–в’ІҚёӮр ҚsӮўҒA ӮЬӮҪ—vүоҢм”F’иӮрҺуӮҜӮҪҗlӮЙ‘ОӮөҒAӢҸ‘оүоҢмҺxүҮҺ–ӢЖ ҺТ ҒiғPғAғvғүғ“Қмҗ¬Ӣ@ҠЦҒjҒAӮЁӮжӮСүоҢм•ЫҢҜҺ{җЭҒi“Б•К—{ҢмҳVҗl ғzҒ[ғҖҒA ҳVҗl•ЫҢ’Һ{җЭҒA—Г—{Ң^•aҸ°ҢQ“ҷҒjӮЙӮЁӮўӮДҒAүоҢмғTҒ[ ғrғXҢvүжҒiғPғAғvғүғ“Ғj ӮМҚмҗ¬ӮвғTҒ[ғrғXӮМҠЗ—қӮрҚsӮӨҗк–еҗEӮМ Ңц“IҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB |
ҒңӢҸ‘оүоҢмҺxүҮҺ–ӢЖҺТ(ғP ғAғvғүғ“Қмҗ¬Ӣ@ҠЦ) ҒңүоҢм•ЫҢҜҺ{җЭ (“Б•К—{ҢмҳVҗlғzҒ[ғҖҒAҳVҗl •ЫҢ’Һ{җЭҒA—Г—{Ң^•aҸ°ҢQ “ҷ) ӮЕҒAүоҢмғTҒ[ғrғXҢvүж (ғPғAғvғүғ“)ӮрҚмҗ¬Ӯ·Ӯйҗк–е җEҒB |
|
|
үоҢм•ҹҺғҺm |
җg‘МӮӘ•sҺ©—RӮИҚӮ—оҺТӮЙҒA“ь—ҒҒE”rҹ•ҒEҗHҺ–ҒEҲЯ•һӮМ’…’EҒEҲЪ“® ӮИӮЗӮМӮіӮЬӮҙӮЬӮИҗgӮМүсӮиӮМүоҢмӮрҚsӮБӮҪӮиҒAүоҢмҺТӮЕӮ ӮйүЖ‘° ӮЦӮМҺw“ұӮвҸ•ҢҫӮрӮөӮҪӮиӮ·ӮйҒAҗк–е“IӮИүоҢм’mҺҜӮвӢZҸpӮрӮаӮБ ӮҪғGғLғXғpҒ[ғgӮӘүоҢм•ҹҺғҺmӮЕӮ·ҒBҺ‘ҠiҺж“ҫӮМӮҪӮЯӮЙӮНүоҢм•ҹ ҺғҺm—{җ¬ҚZӮр‘ІӢЖӮ·ӮйӮ©ҒAӮR”NҲИҸгӮМҺА–ұҢoҢұҢгҒAҚ‘үЖҺҺҢұӮр ҺуҢұӮ·Ӯй•ы–@ӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBүоҢмӢЖ–ұӮЙҸ]Һ–Ӯ·ӮйҗlӮҪӮҝӮМҺ‘ҠiӮМ ҢьҸгӮрӮЯӮҙӮөӮДҒAӮPӮXӮWӮV”NҒuҺРүп•ҹҺғҺmӢyӮСүоҢм•ҹҺғҺm–@ҒvӮЙӮж ӮБӮДҗ¶ӮЬӮкӮҪҚ‘үЖҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB ӮИӮЁҒAҳVҗl•ҹҺғҺ{җЭӮИӮЗӮЕҒA—ҫ•кҒi—ҫ•ғҒjӮЙӮИӮйӮЙӮНҒA–@—ҘҸг“Б •КӮМӢK’иӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮӘҒAҚЕӢЯӮЕӮНүоҢм•ҹҺғҺmӮМҺ‘ҠiӮрӢҒӮЯӮй ӮЖӮұӮлӮӘ‘қӮҰӮДӮ«ӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮЬӮҪҒA–K–вүоҢмҲхӮв—ҫ•кҗEӮМҺА–ұҢo ҢұӮрҠҲӮ©ӮөӮДҒAҺ‘ҠiӮрҺж“ҫӮ·ӮйҗlӮа‘ҪӮӯӮИӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB ҒEҗ¶ҸИӮМҺw’иӮ·Ӯй—{җ¬Һ{җЭӮЕ•K—vӮЖӮіӮкӮйүИ–ЪӮр—ҡҸCӮ·ӮйҒiҚ‘үЖ ҺҺҢұ•s—v) ҒEҚ‘үЖҺҺҢұӮЙҚҮҠiӮ·Ӯй ҒEүоҢмӮЙҠЦӮ·ӮйӢZ”\Ңҹ’иӮЙҚҮҠiӮ·Ӯй |
ҒңҺРүп•ҹҺғҺ{җЭ Ғi“Б•К—{ҢмҳVҗlғzҒ[ғҖҒA —{ҢмҳVҗlғzҒ[ғҖҒA ғfғCғTҒ[ғrғXғZғ“ғ^Ғ[“ҷӮМ ҳVҗl•ҹҺғҺ{җЭҒB җg‘МҸбҠQҺТ—ГҢмҺ{җЭҒA җg‘МҸбҠQҺТҺцҺYҺ{җЭӮИӮЗӮМ җg‘МҸбҠQҺТҚXҗіүҮҢмҺ{җЭҒj ҒңҳVҗl•ҹҺғҺ{җЭҒA җg‘МҸбҠQҺТҚXҗіүҮҢмҺ{җЭӮИ ӮЗӮМ—ҫ•кҒi—ҫ•ғҒjҒA ҚЭ‘о•ҹҺғӮМ’SӮўҺиӮЖӮИӮй–K –вүоҢмҲхӮЖӮөӮД“ӯӮ«ӮЬӮ·ҒB ҒңҚsҗӯӢ@ҠЦ ҒңҺРүп•ҹҺғӢҰӢcүпӮИӮЗ |
|
|
ҠЕҢм•wҒEҠЕҢмҺm |
Ҹқ•aҺТ“ҷӮМ—Г—{ҸгӮМҗўҳbӮЬӮҪӮНҗfҺ@ӮМ•вҸ•ӮрҚsӮӨҗк–еҗEӮМҚ‘ үЖҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB •ҹҺғ•Ә–мӮМҸкҚҮҒA‘ҪӮӯӮНҸyҠЕҢм•wҒEҠЕҢмҺm–ЖӢ–ӮЕ Ӯ ӮБӮДӮаҒAҠЕҢмӮМӢЖ–ұӮЙҸ]Һ–Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB |
•aү@ |
|
|
Ӣ`ҺҲ‘•ӢпҺm |
үҪӮзӮ©ӮМҸбҠQӮЕҺёӮБӮҪҺи‘«ӮМӢ@”\ӮМ‘гӮнӮиӮрӮ·ӮйӢ`ҺҲҒA ғRғӢ ғZғbғgӮИӮЗӮМҺЎ—ГӮр–Ъ“IӮЙӮөӮҪ‘•ӢпӮрҗ»ҚмӮөҒA —ҳ—pҺТӮӘ“ъҸнҗ¶ ҠҲӮр‘—ӮйӮӨӮҰӮЕ•K—vӮИӢ@”\ӮМүс•ңӮрҗ}ӮиҒA ҺРүп•ңӢAӮр‘ЈҗiӮ·Ӯй ғҠғnғrғҠғeҒ[ғVғҮғ“ӮрҚsӮӨҗк–еҗEӮМҚ‘үЖҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB |
|
|
|
ҢҫҢк’®ҠoҺm |
үҪӮзӮ©ӮМҢҙҲцӮЕҢҫҢкҸбҠQӮв“п’®ҒAҺёҢкҒAҢҫҢк”ӯ’B’x‘ШӮИӮЗӮМ ҢҫҢк ҒE’®ҠoӮМҸбҠQӮрӮаӮВҗlӮЙ‘ОӮөҒAҗк–е“IӮИҢP—ыҒEҺw“ұӮрҚsӮўҒA Ӣ@”\үс•ңӮвҸбҠQӮМҢyҢёӮрҗ}Ӯйҗк–еҗEӮМҚ‘үЖҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB |
|
|
|
ҚмӢЖ—Г–@Һm |
ӮnӮs(Occupational Therapist) •aү@ӮвғҠғnғrғҠғZғ“ғ^Ғ[ӮЙӮЁӮўӮДҒAҲгҺtӮМҺw“ұӮМӮаӮЖӮЙҒA җg‘МӮЬ ӮҪӮНҗёҗ_ӮЙҸбҠQӮрӮаӮБӮҪҗlӮЙҒAҚHҚмӮвҺиҢ|ӮИӮЗӮМҚмӢЖҒA җ¶ҠҲ“® ҚмӮМҢP—ыӮИӮЗӮр’КӮ¶ӮДҒA“®ҚмӮМүс•ңӮвӢ@”\’бүәӮМ—\–hӮМҺиҸ•ӮҜ ӮвҒA ҺРүпӮЦ‘ОүһӮЕӮ«ӮйӮжӮӨӮЙҗS—қ“IүҮҸ•ӮрҚsӮӨҗк–еҗEӮМҚ‘үЖҺ‘ ҠiӮЕӮ·ҒB |
|
|
|
ҺӢ”\ҢP—ыҺm |
Ң©ӮйӢ@”\ҒiҺӢ”\ҒjӮЙҸбҠQӮрӮаӮВҗlӮЙҒA Ӣ@”\үс•ңӮМӮҪӮЯӮМҺӢӢ@”\ ҢҹҚёӮЖҺӢ”\ӢёҗіҢP—ыӮрҚsӮӨҗк–еҗEӮМҚ‘үЖҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB |
|
|
|
ҺРүп•ҹҺғҺm |
ҚӮ—оҺТӮӘҲАҗSӮөӮДҒA‘Ҡ’kӮвҸ•ҢҫҒEҺw“ұҒAӮ»ӮМ‘јӮМүҮҸ•ӮрҺуӮҜӮй ӮұӮЖӮМӮЕӮ«Ӯйҗк–еүЖӮЖӮўӮӨҲК’uӮГӮҜӮЕҒAӮPӮXӮWӮVҒiҸәҳaӮUӮQҒj”NҒuҺРүп •ҹҺғҺmӢyӮСүоҢм•ҹҺғҺm–@ҒvӮЙӮжӮБӮДҗ¶ӮЬӮкӮҪҚ‘үЖҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB Ғ@•ҹҺғӮМ“а—eӮвғTҒ[ғrғXӮЙӮВӮўӮДӮМҸо•с’сӢҹҒA•ЫҢ’ҒEҲг—ГҒE”NӢа ӮИӮЗӮМҗ§“xӮвҺ{җЭӮМ—ҳ—p–@ӮМҸРүо“ҷ•ҹҺғғTҒ[ғrғXӮрӢҒӮЯӮйҚӮ —оҺТӮвҸбҠQҺТҒAӮ»ӮөӮДүоҢмӮрӮөӮДӮўӮйүЖ‘°ӮЙ‘ОӮөӮДҗeҗgӮМ‘Ҡ’kҒE үҮҸ•ӮрҚsӮӨҒuҺРүп•ҹҺғӮМҗк–еүЖҒvӮЖӮўӮҰӮЬӮ·ҒB Ғ@ Ғ@ӮИӮЁҒAҺРүп•ҹҺғҺmҺ‘ҠiӮрҺж“ҫӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒAҚ‘үЖҺҺҢұҺуҢұҺ‘ ҠiҺж“ҫҢгӮЙҚ‘үЖҺҺҢұӮЙҚҮҠiӮ·Ӯй•K—vӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB Ңъҗ¶‘еҗbӮӘҺw’иӮөӮҪҺw’иҺҺҢұӢ@ҠЦӮЕӮ Ӯй (Қа)ҺРүп•ҹҺғҗUӢ»ҒEҺҺ ҢұғZғ“ғ^Ғ[ӮӘҺАҺ{Ӯ·ӮйҒuҺРүп•ҹҺғҺmҚ‘үЖҺҺҢұҒv ӮЙҚҮҠiӮөӮИӮҜӮк ӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒB |
ҒңҳVҗl•ҹҺғҺ{җЭҒAҗg‘МҸбҠQ ҺТ•ҹҺғҺ{җЭҒAҺҷ“¶Һw“ұ•ҹҺғ Һ{җЭӮИӮЗӮМҺРүп•ҹҺғҺ{җЭӮМ Һw“ұҲх ҒңҲг—ГӢ@ҠЦӮМғPҒ[ғXғҸҒ[ғJ Ғ[ Ғң‘Ҡ’kӢ@ҠЦӮвҺРүп•ҹҺғӢҰ ӢcүпӮИӮЗӮЕҒA’nҲж•ҹҺғӮЙӮ© Ӯ©ӮнӮйҗк”CҗEҲх ҒңҢц–ұҲхҒmҚ‘үЖҢц–ұҲхҒA’n •ыҢц–ұҲхӮЖӮөӮДҒAҺРүп•ҹҺғ җEҒiҺ{җЭӮИӮЗҒjҒAҲк”КҚsҗӯҗE Ғi•ҹҺғҺ––ұҸҠӮИӮЗҒjҒn |
|
|
җёҗ_•ЫҢ’•ҹҺғҺm |
җёҗ_ҸбҠQҺТӮМ•ЫҢ’Ӯв•ҹҺғӮЙӮВӮўӮДӮМҗк–е’mҺҜҒEӢZҸpӮЙҠоӮГ Ӯ«ҒA җёҗ_ҸбҠQҺТӮМҺРүп•ңӢAӮЙӮВӮўӮДӮМ‘Ҡ’kүҮҸ•ӮрҚsӮӨҗк–еҗE ӮМҚ‘үЖҺ‘ҠiӮЕӮ· |
|
|
|
•ЫҢ’•wҒE•ЫҢ’Һm |
Ғu•ЫҢ’•w(Һm)ҒvӮМ–јҸМӮр—pӮўӮД•ЫҢ’Һw“ұӮЙҸ]Һ–Ӯ·ӮйӮҪӮЯӮМҚ‘үЖ Һ‘ҠiӮЕӮ·ҒB Ӣп‘М“IӮЙӮНҒAҗФӮҝӮбӮсӮМҢ’җfӮвҒAүЖ’л–K–вҒA—\–hҗЪ ҺнҒA җ¬җlӮМ•ыӮМӮўӮлӮўӮлӮИҢ’җfӮвҢ’ҚNӮГӮӯӮиӮМӢіҺәҒAҢ’ҚN‘Ҡ’k ӮвҒAӮЁ”NҠсӮиӮМҢ’ҚNҠЗ—қӮвҒAүЖ’л–K–вӮИӮЗҒB Қ‘үЖҺҺҢұӮМҺуҢұҺ‘ҠiӮНҒAӮS”Nҗ§ӮМҠЕҢм‘еҠwӮр‘ІӢЖӮ·ӮйӮ©ҒAӮЬӮҪ ӮНҒAҠЕҢмҠwҚZӮ©ҠЕҢм’Z‘еҒiӮўӮёӮкӮаӮR”NҒjӮр‘ІӢЖӮө•ЫҢ’•wҠwҚZҒiӮP ”NҒj Ӯр‘ІӢЖӮ·ӮйӮЖ“ҫӮзӮкӮЬӮ·ҒB |
|
|
|
—қҠw—Г–@Һm |
ӮoӮs •aү@ӮвғҠғnғrғҠғZғ“ғ^Ғ[ҒAҳVҗlғzҒ[ғҖӮв—{җ¬ҚZӮИӮЗӮЙӮЁӮўӮДҒAҗg ‘МӮЙҸбҠQӮМӮ ӮйҗlӮЙӢШ—НӮМ‘қӢӯӮИӮЗӮМү^“®—Г–@ҒAү·”M ҒE“dӢCӮИ ӮЗӮрҺgӮБӮҪ•Ё—қ—Г–@Ӯр’ҶҗSӮЙҺ{ӮөҒA“ъҸнҗ¶ҠҲӮр‘—ӮйӮӨӮҰӮЕҠо–{“I ӮИ“®Қм”\—НӮМүс•ңӮрҗ}ӮйҒAӮ ӮйӮўӮНӢк’ЙӮрҳaӮзӮ°ӮйӮИӮЗӮМҺЎ—Г ӮрҚsӮӨҗк–еҗEӮМҚ‘үЖҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB |
|
|
|
ғPғAғNғүҒ[ғN |
үоҢм•ЫҢҜҗҝӢҒҺ––ұӮИӮЗҒAүоҢмҺ––ұӮМҗк–еҗEӮЖӮөӮДҒAӮ»ӮМ’mҺҜӮЁ ӮжӮСӢZ”\Ӯр•]үҝӮө”F’иӮ·ӮйҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB Ғ@үоҢм•ЫҢҜҗ§“xӮЙӮжӮиҒA•ҹҺғҺ{җЭӮв•aү@“ҷӮЕӮНҒAҺsӢж’¬‘әӮЦүо ҢмғTҒ[ғrғXӮМ”п—pӮрүоҢм•сҸVӮЖӮөӮДҗҝӢҒӮ·ӮйӮҪӮЯҒAүоҢм•ЫҢҜӮМ Һ––ұҺи‘ұӮ«ӮЙҸЪӮөӮўғPғAғNғүҒ[ғNӮр•K—vӮЖӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB |
•ҹҺғҺ{җЭҒA•aү@ӮИӮЗ |
|
|
Һҷ“¶Һw“ұҲх”C—p Һ‘Ҡi |
Һҷ“¶Һw“ұҲхӮНҒAҺҷ“¶•ҹҺғ–@ӮЙӮжӮйҺҷ“¶•ҹҺғҺ{җЭӮМҗEҲхӮЕҒAҺҷ “¶ӮМҗ¶ҠҲҺw“ұӮрҚsӮӨҺТӮЖҒAҺҷ“¶•ҹҺғҺ{җЭҚЕ’бҠоҸҖ‘жӮSӮQҸрӮЙӢK ’иӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBҺҷ“¶Һw“ұҲх”C—pҺ‘ҠiӮНҒAҺҷ“¶•ҹҺғҺ{җЭӮӘҺҷ“¶ Һw“ұҲхӮрҚМ—pӮ·ӮйҚЫӮМҠоҸҖӮЖӮөӮД’иӮЯӮзӮкӮҪҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB Ғ@Һ‘ҠiӮрҺж“ҫӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒAҢъҗ¶ҳJ“ӯ‘еҗbҺw’иӮМ—{җ¬Һ{җЭӮр‘І ӢЖӮ·ӮйӮ©ҒA•ҹҺғҒEҺРүпҒEҗS—қҠw•”ҒiҠwүИҒjӮМ‘еҠwӮр‘ІӢЖӮ·ӮйӮ©ҒAӮа ӮөӮӯӮНҸ¬ҒE’ҶҒEҚӮ“ҷҠwҚZӮМӢіҲх–ЖӢ–ҸуӮрҺж“ҫӮ·ӮйӮИӮЗӮМ•ы–@ӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB Ғ@җ¶ҠҲҺw“ұҢvүжӮМ—§ҲДҒAҺqӮЗӮаӮМғOғӢҒ[ғvҺw“ұҒAғPҒ[ғXғҸҒ[ғNҒA Һ{җЭҗEҲхӮМғXҒ[ғpҒ[ғoғCғUҒ[ӮЖӮөӮДӮМ–рҠ„Ӯр’SӮӨӮИӮЗҒAҺ{җЭ“аӮЕ Һw“ұ“IӮИ–рҠ„Ӯр’SӮўӮЬӮ·ҒB |
ҒңҺҷ“¶•ҹҺғҺ{җЭ Һҷ“¶—{ҢмҺ{җЭҒA ’m“IҸбҠQҺҷҺ{җЭҒA ҺҲ‘М•sҺ©—RҺҷҺ{җЭҒA •кҺqҗ¶ҠҲҺxүҮҺ{җЭҒA Һҷ“¶Ңъҗ¶Һ{җЭҒA –УӮлӮӨӮ ҺҷҺ{җЭҒA ҸоҸҸҸбҠQҺҷ’ZҠъҺЎ—ГҺ{җЭҒA ҸdҸЗҗSҗgҸбҠQҺҷҺ{җЭҒA Һҷ“¶Һ©—§ҺxүҮҺ{җЭҒA Һҷ“¶үЖ’лҺxүҮғZғ“ғ^Ғ[ӮИӮЗ |
|
|
ҺРүп•ҹҺғҺеҺ–”C —pҺ‘Ҡi |
•ҹҺғҳZ–@ҒvҒiҗ¶ҠҲ•ЫҢм–@ҒAҺҷ“¶•ҹҺғ–@ҒA•кҺqӢyӮСүЗ•w•ҹҺғ–@ҒA ’m“IҸбҠQҺТ•ҹҺғ–@ҒAҳVҗl•ҹҺғ–@ҒAҗg‘МҸбҠQҺТ•ҹҺғ–@ҒjӮЙҠоӮГ Ӯ«ҒAҠeҚsҗӯӢ@ҠЦӮЙӮЁӮўӮДҒA•ЫҢмҒEүҮҸ•Ӯр•K—vӮЖӮ·ӮйҗlӮҪӮҝӮЙ‘ОӮө ӮДҒA‘Ҡ’kҒEҺw“ұӢЖ–ұӮрҚsӮўӮЬӮ·ҒB Ғ@ Ғ@ҺРүп•ҹҺғҺеҺ–”C—pҺ‘ҠiӮНҒA–{—ҲӮНҢц–ұҲхӮӘ•ҹҺғҺ––ұҸҠӮИӮЗ ӮМ•ҹҺғҚsҗӯӮМҺdҺ–ӮЙҸ]Һ–Ӯ·ӮйӮЖӮ«ӮЙ•K—vӮЖӮіӮкӮй—vҢҸӮЕӮ·ҒBӮВӮЬ ӮиҒAҺРүп•ҹҺғҺеҺ–”C—pҺ‘ҠiӮр“ҫӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНҒA‘еҠwӮв—{җ¬ҚZӮЕ ҺРүп•ҹҺғӮЙҠЦӮ·ӮйҺw’иүИ–ЪӮр—ҡҸCӮөҒA‘ІӢЖӮөӮҪҒAӮЖӮўӮӨҲУ–ЎҚҮӮў ӮИӮМӮЕӮ·ҒBҢц–ұҲхҺҺҢұӮЙҚҮҠiӮө•ҹҺғҺ––ұҸҠӮИӮЗӮЙ”z‘®ӮіӮкӮДҒAҸү ӮЯӮДҺ‘ҠiӮЖӮөӮД”F’иӮіӮкӮйӮаӮМӮЕҒAҚ‘үЖҺ‘ҠiӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBҒu”C —pҺ‘ҠiҒvӮНҒA‘јӮМҚ‘үЖҺ‘ҠiӮв”F’иҺ‘ҠiӮЖӮНҲбӮўҒAҺҺҢұӮИӮЗӮрҺу ӮҜҒAӮ»ӮМҚҮ”ЫӮЙӮжӮБӮД“ҫӮзӮкӮйӮаӮМӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB‘еҠwҒE’Z‘еҒE җк–еҠwҚZӮИӮЗӮЕҺw’иӮіӮкӮҪүИ–ЪӮр—ҡҸCӮөӮҪӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮЕҢҲӮЯӮзӮкӮД ӮўӮйӮҪӮЯҒAҺРүп•ҹҺғҺmӮвүоҢм•ҹҺғҺmӮЖӮНҗ«ҠiӮӘҲЩӮИӮиӮЬӮ·ҒB Ғ@ӮҪӮҫӮөҒAҺРүп•ҹҺғҺm–@‘жӮPӮXҸрӮЙӢK’иӮіӮкӮҪҺРүп•ҹҺғҺеҺ–”C—p Һ‘ҠiӮНҒAҳVҗlғzҒ[ғҖҒAҸбҠQҺТ•ҹҺғҺ{җЭҒAҺҷ“¶•ҹҺғҺ{җЭӮИӮЗӮМҺw “ұҲхӮЙӮИӮйҺ‘Ҡi—vҢҸӮЙӮа’иӮЯӮзӮкҒAҚМ—p—vҢҸӮЖӮИӮБӮДӮўӮйғPҒ[ғX ӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB |
’n•ыҺ©ҺЎ‘МӮМ•ҹҺғҺ––ұҸҠ ӮМғPҒ[ғXғҸҒ[ғJҒ[ ҳVҗl•ҹҺғҺ{җЭӮвҸбҠQҺТ•ҹ ҺғҺ{җЭӮМҗ¶ҠҲҺw“ұҲхӮИӮЗ |
|
|
”F’иҗS—қҺm |
җS—қҠwӮМҗк–еүЖӮЖӮөӮДҺdҺ–ӮрӮ·ӮйӮӨӮҰӮЕ•K—vӮИҒA•WҸҖ“IҠо‘bҠw —НӮЖӢZ”\ӮрҸC“ҫӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮрҸШ–ҫӮ·ӮйҺ‘ҠiӮЖӮөӮДҒAҗS—қҠwҢnӮМ4 ”Nҗ§‘еҠwӮр‘ІӢЖӮөӮҪҗlӮр‘ОҸЫӮЙ”F’иӮіӮкӮйҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB‘еҠw‘ІӢЖ ҺһӮЙҺР’c–@җl“ъ–{җS—қҠwүпӮЙҗ\җҝӮ·ӮйӮұӮЖӮЕҺж“ҫӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB•ҹ ҺғғTҒ[ғrғXӮМ—ҳ—pҺТӮЙӮНҒAүҪӮзӮ©ӮМҗSӮМҸқӮр•шӮҰӮҪҗlӮа‘ҪӮӯҒAӮұ ӮМҺ‘ҠiӮН•ҹҺғӮМӮ°ӮсӮОӮЕўҗSӮМғPғAЈӮрҚsӮӨҚЫӮЙ–р—§ӮҝӮЬӮ·ҒB |
ҳVҗl•ҹҺғҺ{җЭ ҸбҠQ•ҹҺғҺ{җЭ Һҷ“¶•ҹҺғҺ{җЭӮИӮЗҺРүп•ҹҺғ Һ{җЭӮМҺw“ұҲх Ҳг—ГӢ@ҠЦӮМҲг—Гғ\Ғ[ғVғғғӢ ғҸҒ[ғJҒ[ ҺРүп•ҹҺғҺ{җЭҒE•aү@ҒEҠwҚZҒE Ҳк”КҠйӢЖӮИӮЗӮМғJғEғ“ғZғү Ғ[ |
|
|
•ҹҺғҸZҠВӢ«ғRҒ[ ғfғBғlҒ[ғ^Ғ[ |
•ҹҺғҸZҠВӢ«ғRҒ[ғfғBғlҒ[ғ^Ғ[ҒiӮRӢүӮ©ӮзӮPӢүҒjӮНҒAӮЁ”NҠсӮиӮвҸбҠQ ӮрҺқӮҪӮкӮҪ•ыӮЙ‘ОӮөӮДҒAҸZӮЭӮвӮ·ӮӯҲА‘SӮИҸZҠВӢ«Ӯр’сҲДӮ·ӮйғAғh ғoғCғUҒ[ӮЕӮ·ҒB•ҹҺғҒEҲг—ГҒEҢҡ’zӮЙӮВӮўӮД•қҚLӮў’mҺҜӮрҗgӮЙӮВ ӮҜҒAғ\Ғ[ғVғғғӢғҸҒ[ғJҒ[ӮвҢҡ’zҠЦҢWҺТҒA—қҠw—Г–@ҺmӮИӮЗӮМҗк–е үЖӮЖҳAҢgӮрҺжӮиӮИӮӘӮзҒA“KҗШӮИҸZ‘оүьҸCғvғүғ“Ӯр’сҲДӮөӮЬӮ·ҒBӮЬ ӮҪҒAҠeҺнӮМ•ҹҺғғTҒ[ғrғXӮвҺуӮҜӮзӮкӮйҸ•җ¬ӢаҒA•ҹҺғ—pӢпҒEүоҢм —p•iҒEүЖӢпӮИӮЗӮМ‘I‘рӮв—ҳ—p•ы–@ӮМғAғhғoғCғXӮИӮЗӮаҚsӮўӮЬӮ·ҒB |
ҚЭ‘оүоҢмҺxүҮғZғ“ғ^Ғ[ ҚӮ—оҺТҗ¶ҠҲ•ҹҺғғZғ“ғ^Ғ[ ҳVҗl•ЫҢ’Һ{җЭ •aү@ӮИӮЗ Ңҡ’zҗЭҢvҺ––ұҸҠ ҸZ‘оҗЭ”хғҒҒ[ғJҒ[ӮИӮЗӮМҠй ӢЖ |
|
|
•ҹҺғ—pӢпҗк–е‘Ҡ ’kҲх |
—ҳ—pҺТӮЙҚҮӮБӮҪ•ҹҺғ—pӢпӮМ‘I’и‘Ҡ’kӮИӮЗӮрҚsӮӨҗк–еҗEӮМӮҪӮЯ ӮМҚ‘үЖҺ‘ҠiӮЕӮ·ҒB•ҹҺғӢ@Ҡн—pӮМғҢғ“ғ^ғӢғTҒ[ғrғXӮрҚsӮӨҺw’и•ҹ Һғ—pӢп‘Э—^Һ––ұҸҠӮЕӮНҒA•ҹҺғ—pӢпҗк–е‘Ҡ’kҲхӮЖӮөӮДҒAүоҢм•ҹҺғ ҺmҒAҺРүп•ҹҺғҺmӮИӮЗӮМ—LҺ‘ҠiҺТӮр•KӮёҸнӢОӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮӘӢ`–ұ•t ӮҜӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB |
•ҹҺғӢ@ҠнӮМғҢғ“ғ^ғӢғTҒ[ғr ғXӮрҚsӮӨ–ҜҠФҠйӢЖӮИӮЗ |
|
|
–K–вүоҢмҲх (ғzҒ[ғҖғwғӢғp Ғ[) |
үЖ‘°ӮӘҸ\•ӘӮИүоҢмӮрӮЕӮ«ӮИӮўҚӮ—оҺТҒAӮРӮЖӮи•йӮзӮөӮМҚӮ—оҺТҒA җg‘МҸбҠQҺТӮв’m“IҸбҠQҺТӮМүЖ’лӮр–K–вӮөҒAӮ»ӮкӮзӮМҗlҒXӮМҗgӮМ ӮЬӮнӮиӮМүоҢмӮвүЖҺ–ӮМүҮҸ•ӮрӮөӮЬӮ·ҒB–K–вүоҢмҲхҺ‘ҠiӮЙӮНӮRӢү Ӯ©ӮзӮPӢүӮЬӮЕӮӘӮ ӮиҒAӮRӢүӮНүЖҺ–үҮҸ•ӢЖ–ұҒiҗҶҺ–Ӯв‘|ҸңҒA”ғӮў •ЁҒA’Кү@ӮМ•tӮ«“YӮўӮИӮЗҒjӮЙҺdҺ–ӮӘҢАӮзӮкҒAҗg‘МүоҢмӢЖ–ұӮрҚsӮӨ ӮЙӮНӮQӢүҲИҸгӮМҺ‘ҠiӮӘ•K—vӮЕӮ·ҒBӮQӢүӮЕӮНҺеӮЙҗQӮҪӮ«ӮиӮМӮЁ”N ҠсӮиӮИӮЗӮМүоҢмӢЖ–ұӮр’S“–ҒBӮPӢүӮЕӮНҒAҲг—ГғXғ^ғbғtӮвғPҒ[ғXғҸ Ғ[ғJҒ[ӮЖҳAҢgӮөӮДҚsӮӨғ`Ғ[ғҖү^үc•ыҺ®ӮМғzҒ[ғҖғwғӢғvғTҒ[ғrғXӮМ ’ҶҗS“I–рҠ„Ӯр’SӮўӮЬӮ·ҒB Ғ@Һ‘ҠiҺж“ҫӮМӮҪӮЯӮЙӮНҠe“s“№•{Ң§’PҲКӮЕҺАҺ{ӮіӮкӮДӮўӮй—{җ¬Қu ҸKӮрҸC—№Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘ•K—vӮЕӮ·ҒBҒ@Ғ@2ӢүҺАӢZғXғNҒ[ғҠғ“ғOӮМ—lҺq |
ҒңҺРүп•ҹҺғ–@җl “Б•К—{ҢмҳVҗlғzҒ[ғҖ ҚЭ‘оүоҢмҺxүҮғZғ“ғ^Ғ[ ҺРүп•ҹҺғӢҰӢcүпӮИӮЗ ҒңғzҒ[ғҖғwғӢғpҒ[”hҢӯӮв“ь —ҒҸ„үсғTҒ[ғrғXӮИӮЗӮрҚsӮӨғV ғӢғoҒ[ғrғWғlғXҺYӢЖ ҒңҺsӢж’¬‘әӮМҢц–ұҲх |
|
|
—ХҸ°җS—қҺm |
җS—қ“IӮИ–в‘иӮрҺжӮиҲөӮӨўҗSӮМҗк–еүЖЈӮЕӮ·ҒB‘Ҡ’kҺТ(ғNғүғCғAғ“ғg) ӮЙ‘ОӮөҒAӮіӮЬӮҙӮЬӮИӢZ–@Ӯр—pӮўӮДҗS—қ“I–в‘и“_Ӯр•ӘҗНӮөҒA–в‘иүь ‘PӮЙҢьӮҜӮДӮМүҮҸ•ӮрҚsӮўӮЬӮ·ҒBӮЬӮҪҒAҠwҚZӮвҗEҸкӮИӮЗӮЕғJғEғ“ғZ ғүҒ[ӮЖӮөӮДӮМүҮҸ•ӮаҺdҺ–ӮМҲкӮВӮЕӮ·ҒBҺ‘ҠiҺҺҢұӮрҺуӮҜӮйӮҪӮЯӮЙ ӮНҒA“ъ–{—ХҸ°җS—қҺmҺ‘Ҡi”F’иӢҰүпҺw’иӮМ‘еҠwү@Ӯр‘ІӢЖӮөҒAҺА–ұ ҢoҢұ(ҮTҺнҺw’и‘еҠwү@‘ІӢЖӮМҸкҚҮӮН•s—v)ӮрҢoӮДҺуҢұҺ‘ҠiӮр“ҫ ӮйӮұӮЖӮӘ•K—vӮЕӮ·ҒB |
•aү@ (җ_ҢoүИҒAҗёҗ_үИҒAҗS—Г“а үИҒj җёҗ_•ЫҢ’•ҹҺғғZғ“ғ^Ғ[ ҠйӢЖ“аҗf—ГҸҠӮИӮЗ Һҷ“¶‘Ҡ’kҸҠ Ҹ¬“пҠЦ•КҸҠ ғfғCғPғAғZғ“ғ^Ғ[ Ҹ¬’ҶҚӮӮМғXғNҒ[ғӢғJғEғ“ғZ ғүҒ[ Ҡwҗ¶‘Ҡ’kҺә ӢіҲз‘Ҡ’kӢ@ҠЦӮИӮЗ |
|
|
|
 Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
