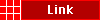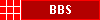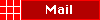|
豊島・新宿支部
   

ヘルパー2級講座
スクーリング(実技/通学学習)
介護する側とされる側になって技術を学びます。
利用者の気持ちを理解して、思いやりのある介護を体得。
8日間(9:30~17:30)
4日目
・食事の介護
・車いす等での移動の介護
・車いすへの移乗等の介護
・肢体不自由者の歩行の介護
・視覚障害者の歩行の介護 |
|
1.食事の基礎知識
(1)食事の意義
(2)栄養素とそのはたらき
(3)食事を取るプロセス
(4)食事摂取から排泄までの仕組み
2.高齢者の食事の特徴
(1)老化に伴う食事摂取能力の低下の要因
①咀嚼機能の低下 調理方法の工夫
②嚥下機能の低下
③消化吸収能力の変化
④感覚機能の低下
⑤運動機能の障害
⑥利用者の心理、介護者との関係
(2)食事摂取量の低下の影響
3.食事摂取困難への対応
(1)嚥下障害 窒息・誤嚥性肺炎
(2)脱水 くれぐれも注意が必要 部屋の湿度などにも留意
・食事の介護
側臥位をとり、腰や背中にタオルをあてがい安楽した体位を保持
誤嚥防止(しっかり覚醒)--首を前屈、体を起こす、口腔内を清潔に
うがい
顔を横に倒し、健側の口の端にストローを入れる(左手にコップ、タオルを持った右手でストロー固定)
ガーグルベースン(受け取りの器)を口角部分に合わせる(左で持ち、右でタオルをこぼさないように下へ当てる)
食べ物を口へ運ぶ(健側の口端へお箸やスプーンで)
一口の大きさ、分量、温度、咀嚼のスピードをチェック
随時水分補給を心がける---『お飲み物はおのみになりますか?』『お茶はいかがですか?』とたずねて
口腔清拭の介助---安定した起座位で
割り箸に綿を巻きつけ綿棒を作る
左半分---歯の裏側奥→手前真中 表側 上面も
右半分---歯の裏側→表側→上面
舌苔を除去(奥から手前)
歯ブラシを使用する場合、スプーンの裏側を内側のほほにあて口腔内を大きくして行う
・車いす等での移動の介護
段を上がる
キャスターを段の前につけ、ティッピングレバーを踏み込んでキャスターを上げる
キャスターを段上に乗せ、大車輪を段に押し付けるようにする
グリップを持ち上げ、大車輪を浮かして段上に乗せる
段を下がる
後ろ向きで下りる。グリップを持ち上げ、大車輪を浮かして段から下ろす
ティッピングレバーを踏み込んでキャスターを上げる
キャスターを上げたまま後ろに下がり、キャスターを段から下ろす(ティッピングレバーは踏んで・・・ゆっくりおろす)
・車いすへの移乗等の介護
仰臥位→ベッド端座位→車いすへ
①足を組む(健側で患側をすくって)
②側臥位になりながらベッドの外へ両足を下ろす
③体を起こす(右手で柵を握り、肘をベッドについて、軸にして、上肢を起こす)
④車いすは健側に対し斜めに20~30度
⑤立ち上がり、車椅子のアームレストをつかみ、身体を回転させて、腰を下ろす
 
・肢体不自由者の歩行の介護
・視覚障害者の歩行の介護
半歩前に立ち『わたしの肘を持ってください』と言葉をかけ肘のすぐ上を持ってもらい、腕が横に開かないように脇を絞める
常に道の真中に誘導する--歩きやすいところへ誘導
細い道はZゼット型--道の手前でいったん止まり状況を伝え、誘導している腕を後ろに回し、
真後ろになるように移動してもらう 腕は肩に乗せてもらうか後ろ手に回し持ってもらう
いすへの誘導
いすの後ろまで誘導し(左側からの場合)、いったん止まり、説明する
左手をいすの背もたれへ、右手は据わる面へ誘導、いすの形や向きを手で確認してもらう
腰を下ろすときに、ウエスト部分を支える(身体の向き、距離を誘導)
離れるときは確認して了解が得られればその場を離れる
階段
のぼり---階段の前に直角に止まり、上り階段であることを伝える
片足だけ一段上り、足先での確認できるまで待つ 階段の終わりを告げる
くだり---階段の前に直角に止まり、伝える
片足だけ一段下り、確認できれば下り始める 階段の終わりを告げる
|
|
|

   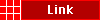 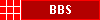 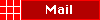 
|