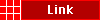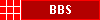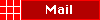|
豊島・新宿支部
   

ヘルパー2級講座
スクーリング(実技/通学学習)
介護する側とされる側になって技術を学びます。
利用者の気持ちを理解して、思いやりのある介護を体得。
8日間(9:30~17:30)
3日目
・体位・姿勢交換の介護
・衣服の着脱の介護 |
|
1、腰痛の予防等援助者の健康管理
ボディメカニクスにかなう介護技術を習熟しておく
基本原則
①重心は低い方が安定する 静止立位の重心はへその当り、常に腰を落とす、低く(腰を曲げない)
②支持基底面積を広くする
③持ち上げる物は、体に接近させる
④腰と肩は平行に保ちねじらない
⑤大きい筋群を使い、平行移動させる
⑥てこの原理を応用する
精神的な健康障害--ストレスにうまく対処しないと燃え尽き症候群(バーンアウト)を起こす
極度の身体の疲労感、逃避的・卑下的になり、行動異常を伴う
2、感染症の予防と理解
(1)介護に注意すべき感染症とその対応
①かぜ(感冒)
②肺炎
③インフルエンザ
④結核
⑤MRSA メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
⑥食中毒
⑦ウイルス性肝炎
⑧エイズ 後天性免疫不全症候群(AIDS)
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染--血液を介した感染
⑨そのほかの感染症
疥癬かいせん--ヒゼンダニによる皮膚病粟粒状のブツブツや水泡ができ
強いかゆみがある。直接接触によって伝染。
梅毒ばいどく--梅毒トレポネーマというスピロヘータ(微生物の一種)により感染
(2)感染予防の注意事項
①手洗い
②うがい
③エプロン
④唾液、吐物、排泄物、血液などには触らない
⑤手指の傷 ゴム手袋
3、体位、姿勢交換の基礎知識
(1)動くことの意義 寝たきりにならないため→痴呆予防 褥瘡予防
(2)廃用症候群(寝たきり症候群)
●代表的な症状
①精神機能(知的活動)の低下
②筋肉の萎縮、筋力低下
③心肺機能の低下
④関節拘縮
(3)体位について
種類--仰臥位(あおむけ)、側臥位(横向き)、腹臥位(うつぶせ)
座位、端座位(ベッドの端に腰掛け、足を垂らした体位)
長座位(上体を起こし足を伸ばした体位)、立位(立つ)
・体位・姿勢交換の介護
ポイント---事前の確認(褥瘡の誘因となる物はないか)
介護中(褥瘡の有無・部位の確認、姿勢保持、圧迫予防のクッション・バスタオルの用意)
事後確認(顔色、表情を観察 利用者の身体状態を把握) *起立性低血圧に注意
最低2時間ごとの体位変換
水平移動 仰臥位→左右側臥位
体をコンパクトにする
腕を組んで小さくまとめる(向く側の腕が下)・・・左側臥位なら左腕が下でおなかの上で両腕クロス
膝を高く立てる
膝と肩を持って静かに手前に引く
肩と腰の2点をしっかりと支え、手前に半回転
腰を引いて安定させる 体を『く』の字に曲げる
上方移動 ビニールを利用者の下に敷く--滑りやすい
体をコンパクトにする
体幹の接触面を小さくする
左腕---利用者の肩甲骨部
右手---利用者の組んだ前腕
一気に斜めに引き上げる
ベッド上での座位 仰臥位→端座位
①声かけ
②ベッド位置(高さ・低さ) 介護しやすいように自分に合わせる
③体を手前に引き寄せる(水平移動) 左手で首の下から肩甲骨を持ち右手はベッドの奥、利用者を引き寄せる
④左手は首の下を右手で両膝下を持ち(利用者の手は自分の肩に)両膝下を持ち上げる
⑤上体を起こしながら体を回転させて両足を降ろす
ベッドからいすへの移乗 端座位→立位→いすへ
①利用者を端に座らせる
②お辞儀をするように首に両手を回してもらい、利用者の両腕を抱えながら持ち上げる
(右足は利用者の足の間、左足はいすの後方へ引いておく)利用者の右足はいすの前に
③臀部を軸に90度回転させる
④身体が安定していることを確認
⑤移乗動作
健側に対して20~30度斜めにいすを置く
利用者の腰の後ろに腕を回す
足の位置--両足で利用者の両膝を挟む
回転両足裏の母趾球を軸にして身体を回転させながらストン (必ず腰の重心低く)
4、褥瘡(床ずれ)の介護
(1)褥瘡とは 「床ずれ」--局所に循環障害が起こり壊死や腫瘍ができた状態
(2)褥瘡の原因
①圧迫 筋力の低下、皮下脂肪の減少により体圧の影響を受けやすい
②ずれ 不安定な体位 シーツのしわ
③摩擦 シーツ、寝巻きによる摩擦
④湿潤 失禁 汗 飲み物をこぼしたなどで蒸れている
⑤不潔 失禁 皮膚や下着、寝巻きが汚れている
⑥低栄養 たんぱく質不足や低栄養→傷ができやすく治りにくい
(3)褥瘡の好発部位
骨の突起している部位、体重のかかるところ全て 耳にまで発生するって・・・痛い!!
1、衣服着脱の基礎知識
(1)衣類着脱の意義
生理的側面--体温調節、危険因子から守るため、汚れない、清潔に保つ
心理的側面--自己表現、好み
社会的側面--TPOにあわせ人間関係を潤滑に、制服・作業着、仕事によって、目的によって
(2)高齢者に適した衣類
衣類の素材と機能
ユニバーサルファッション--誰にでも優しい
目的に合わせたい類の選択 じんべい上下など--軽い・保湿・材質 洗濯簡単!!
2、着脱の援助
(1)着脱時の注意点 利用者の腕や足、体を動かすのではなく、衣類をスぅーッと引く・動かす
①着替えの動作の原則 『脱健着患』脱ぐときは健康な側から着るときは麻痺側から
②部屋の温度にチュウイし、寒ければ介護者の手も暖める
③不必要な露出は避け、本人のプライバシーを守る
④自力で体位交換(寝返りなど)できない場合、背中、腰など下になる部分のしわに注意
・衣服の着脱の介護
1、利用者の麻痺側に立つ
2、自分で着脱できるように誘導する <脱健着患>
麻痺側から袖を通す--袖口、裾をたくし上げ手を入れ利用者の手を取り、肩まで衣類をずらす
3、脱ぐとき ●トレーナー 健側上肢→頭部→麻痺側上肢
●ズボン 健側下肢→麻痺側下肢 麻痺側に立ち、介助する 健側は自力
・ベッド上臥床にて浴衣着脱の介護(左麻痺)
①袖の脱ぎ方 健側に立ち、健側(右)肩を抜く・・・冷えないように暖める
<脱健> 足を少し浮かせてもらい体の下に脱いだ服を入れ込む内側の汚れ・ごみを巻き込んで
右側臥位(健側を下)・・麻痺側上肢は手、肘関節を保持しながら作業<着患>
②新し寝巻き 新しい浴衣の襟にある中心線を利用者の首中心に合わせる
<浴衣> 迎え手をする--手首を通し、手は引かず着物だけを引く(何でも)
しわを取る--ウエスト・尻下・足元の端を斜め下に引く感じで。足元はゆとりを
仰臥位になり新しい着物を引き出して健側の袖を通す 襟は右前
介護用語
臥床がしょう
仰臥位ぎょうがい
端座位たんざい
健側けんそく
患側かんそく
|
|
|

   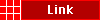 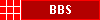 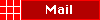 
|